乗車便の決定と乗車券の予約・購入
長距離を移動する際にまず思い浮かぶのは飛行機、そして新幹線…といった感じで考える人は多く、
長距離バスは決してメジャーな存在とは言えません。実際その存在すら知らない…という人も少なくないでしょう。
しかし、このページを見て「夜行バス」という存在を知れば、夜行バスという選択肢を考えない手はないでしょう。
でも、「夜行バス」ってどれに乗って、どうやって乗車券を購入すればよいのでしょうか。
最大の情報源は「時刻表」
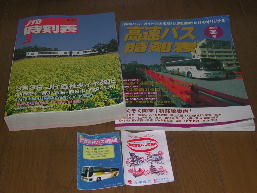 夜行バスをはじめとする高速バスの情報を入手する一番確実な手段は、やはり「時刻表」です。
夜行バスをはじめとする高速バスの情報を入手する一番確実な手段は、やはり「時刻表」です。
書店で千円ほどで売られている大判の時刻表にはJTBが発刊する「時刻表」と交通新聞社が発行する「JR時刻表」がありますが、どちらも夜行および昼行のハイウェイバスの時刻が全線掲載されています。冊子の後方のページになってはいますが、ページの縁に印がついているため割に探しやすいところにあります。
また、もう少しコンパクトで安価なポケット判の小さなものであっても夜行バスの時刻表は載せられています。
交通新聞社からは「高速バス時刻表」という専用の時刻表も発売されています。
なお、夜行バスを運行しているバス会社のバスターミナルには、そのターミナルから出る夜行バスの時刻表は置いてあり、そのほとんどは無料で入手できます。
運賃や停車地なども詳しく書かれていますので、事前に一度調べておきましょう。意外な発見があるかもしれません。
写真:夜行バスの最大の情報源「時刻表」。
右上がその名の通り高速バス専用の「高速バス時刻表」(交通新聞社)。
下の2つはバス会社が出しているもの(西鉄・九州産交)
インターネットも有効な情報源に
近年インターネット接続が家庭にも急速に普及しています。
各バス会社も多くが自社のホームページに情報を掲載するようになりました。中にはモバイル端末(iモードなど)に対応したページを作成しているところもあります。
当「夜行バスに乗ろう!」ページにも、全国の夜行バスを運行する会社(事業者)へのリンクを設けていますのであわせてご利用ください。
→「全国夜行バス会社(事業者)リンク集」(全国夜行バス路線の検索機能がついています)
(別のウィンドウで開きます)
また、「高速バス時刻表」「JR時刻表」などで知られる交通新聞社では「どこなびドットコム」(http://www.doconavi.com/)という交通機関の情報に関するサイトを開設していて、バス路線についても詳しい情報が掲載されています。
その他、全国のバスファンが個人的に各バス会社について詳しい情報を掲載していることもあります。バス会社のオフィシャルページよりもはるかに詳細な情報を網羅していることも決して少なくありません。
なお、個人のページに書かれている情報を参考にする場合は、掲載されている情報が最新のものかどうかについては十分にご注意ください。中には数年か更新されておらず、現状と一致していない場合もあります。
夜行バスの「きっぷ」(乗車券)の購入
夜行バスや長距離高速バスの場合、事前に乗車券を購入しておくのが一般的です。
特に夜行バスに関しては99%事前に予約して座席指定を受ける「予約指定制」です。
乗車券の購入の流れは、まず予約を行ってから乗車券を発行してもらう…という流れが一般的です。ただし、予約と同時に乗車券を発券することもあります。
また、(現在では一部の路線に限られていますが)インターネットやコンビニエンスストアに設置してある端末を利用して「きっぷ」の予約・発券ができます。
支払い方法については基本的に現金払いですが、旅行代理店で購入した場合はクレジットカードが利用できるところもあります。
なお、運賃は中学生以上(12歳以上)が「大人(通常)運賃」、小学生以下(6歳〜12歳)は「小人運賃(通常は大人運賃の半額)」となります。
通常の路線バスでは、大人がつれている幼児(6歳未満)は1人無料になりますが、高速バスでは座席を単独で使用する場合は6歳未満でも小人運賃になります(バス会社によって取り扱いが異なる場合がありますので、詳細はバス会社にお問い合わせください)。
夜行バスの「きっぷ」の発売開始日は、「往路乗車日の1ヶ月前から」というところが多いですが、バス会社によって若干異なります(「1ヶ月1日前から」というところや「3ヶ月前から」「30日前から」などというところもあります)。
座席の予約から乗車券を受け取る(発券)まで
電話で予約します
時刻表やパンフレットなどに運行会社「予約センター」の電話番号が記載されていますので、そこに電話して予約を行います。
夜行バスの多くは複数の会社が共同で運行を担当していますが、出発地に近いところの担当会社でかまいません。
そこで、自分の乗車したい路線名(行先・愛称など)や乗車時刻・乗車地(途中停留所から乗る場合は特に)・乗車人数(男女の別を聞かれる場合もあります)などを伝えます。
無事予約が成功したら、自分の名前・電話番号を伝えます。
その後、「予約番号」(電話番号をそのまま予約番号として用いることも多い)が伝えられた上で「○日までに乗車券を購入してください」という指示があるはずです。
その後、その期限内にバス会社の窓口や旅行代理店などで「予約をすでに行っている」旨を伝えれば乗車券が発券してもらえます。その際に予約番号または電話番号を伝えます。電話予約後、定められた期限までに発券を済ませないと、予約が自動的に取り消されますので注意が必要です。
なお、JRバスの一部路線などでは電話予約はできません(JRバスについては後述)。
バスターミナル・バスセンターで購入
バスが停車するバスターミナル(バスセンター)に発券窓口がある場合は、そこで購入することができます。
窓口で自分が乗りたい便を正しく伝えて(たとえば「2月21日夜(20時20分)発の京都行き」というように)予約を行い、乗車券を発券してもらいます。
その場で予約と同時に購入することもできますし、電話で予約した券を購入することもできます。
旅行代理店で予約から発券まで行う場合
旅行代理店でも予約済みの乗車券を購入できる他、予約と発券を同時に行うことができます。
旅行代理店の窓口に、自分が乗ろうとしている路線(○時×分発の○○行き)を正確に伝えた上で「クーポン」を発行してもらいます。
当日は、旅行会社が発行するクーポンを持って乗車します。クーポンが乗車券の代わりになることがほとんどです。
ただし、ほとんどの場合発券に時間がかかることは覚悟する必要があるでしょう(店員が不慣れなところがけっこう多いのです)。
また、一部オンライン化されているところを除いて「旅行会社側でバスセンターに電話をかけて座席を確保する」ということになるので
バスセンターの営業時間内(だいたい18:00よりも前)に行った方が早く発券してもらえます(バスセンターの営業時間外に行った場合、乗車券の受け取りが翌日以降になることもあります)。
なお、旅行会社とバス会社の契約の関係もあるので、すべての路線で発券できるとは限りません。JTB・近畿日本ツーリスト・日本旅行の大手3社であればたいていの路線は大丈夫なはずです(100%とはいきませんが)。
鉄道会社系の場合、その会社が共同運行関係にあるバス会社であれば(直接共同運行してなくても)だいたい予約できるようです。
たとえば西鉄系の「西鉄旅行」の場合、かつてはサンデン交通(山口)が運行する下関-東京線(「ふくふく東京」号・中国JRバスと共同運行)の発券はできなかったのですが、
西鉄とサンデン交通で福岡天神-下関の高速バスを共同運行するようになった現在では下関-東京線も発券が可能になりました。
なお、旅行代理店で発券を行う場合、路線によっては(乗車券の運賃とは別に)手数料を請求されることがあります(手数料がかかる場合、だいたい300円〜500円程度)ので事前に確認しておくことをおすすめします。
JRバス運行路線の場合
JRバスが運行する夜行バスの場合、全国各地の駅や旅行代理店に設置されている「みどりの窓口」でバスの乗車券も購入できます。全国どこの窓口でも購入可能で、たとえば「下関-東京線(「スーパーふくふく」号)」を熊本の「みどりの窓口」で購入するようなことも可能です。
ただし、「みどりの窓口」の職員はバスの発券に慣れていないところがほとんどで結構手間取ることが多いです。
「みどりの窓口」が1つしかないような小さな駅でラッシュ時に買うのは混雑を招きますので避けた方が賢明でしょう。
なお、JRバスと民間会社が共同運行を行っていることもありますが、
そのような場合は民間側では電話予約を受け付ける場合(サンデン交通など)と電話予約を受け付けない場合(南海電鉄など)があります。
インターネットやコンビニでの予約・発券
三共システム工房の「発車オーライネット」(http://www.j-bus.co.jp/)では、(一部の路線に限られますが)インターネットを利用して予約を行うことができます。「発車オーライネット」で予約した後、ローソンやファミリーマートなどのコンビニエンスストアで乗車券を発行してもらうこともできます。
また、全国の「ファミリーマート」および神奈川中心に店舗展開している「スリーエフ」では、コンビニに設置されている端末で乗車券の予約から行うこともできます。
コンビニ店頭に設置されている端末(「Famiポート」や「Loppi」など)に予約した内容を入力します。
すると端末から「引換票」が印字されますので、その「引換票」をレジに持っていって代金と引き替えに乗車券を受け取ります。
「引換票」には有効期限が記載されています(通常発行後30分以内)。時間内にレジに持っていかないと予約そのものが無効になります(コンビニでは「発券せずに予約だけを行う」ということはできません)。
また、コンビニで発券の場合は一部旅行代理店でかかる「手数料」はかかりません(乗車券の代金のみで発券できます)。が、購入した乗車券を変更・取り消しする場合の手続きや手数料は通常と異なります。ご注意ください。
詳細は、そのコンビニ端末の説明やバス会社のホームページなどをご参照下さい。
現状ではコンビニで予約・発券が可能な会社は限られていますし、可能な会社でも全路線が対応しているとは限らないので気をつける必要があります。
もし事前に乗車券を購入できなかったら…
もし事前にきっぷを買うことができない場合は、なるべく早くバス会社に連絡して指示を仰ぎましょう。
たいていの場合は、当日ターミナルでの購入が可能なはずです。
予約すら取れずに急に乗ることになった場合(当日の飛び込み乗車)は、ほとんどの路線において、予約受付の段階で空席があればたいていは乗車可能です。
その場合は車内またはターミナルで精算になります。
もし、不運にも予約段階で空席がなかった場合は「キャンセル待ち」ということになります。
「キャンセル待ち」の場合は、最後の乗車地で待っているのが普通です(ただし最後の乗車地で乗る客が少ない場合などは例外もあるので、バス会社に確認した方が無難です)。
これは最初の停留所で乗るはずの人が乗ってこなかったとしても、乗車地を変更して後で停車する停留所から乗ってくる可能性があるからです(詳しくは後述)。
特に夜行バスの場合は「キャンセル待ち」がかなわなかった場合、代替手段がなくなっっていることが多いので、いずれにしても(可能であれば)早めにバス会社に連絡をとりましょう。
「満席」!そんなときは…
夜行バスは複数の会社で運行されており、それぞれの会社で予約業務を行っています。ある会社で「満席」といわれた場合でも、他の共同運行会社の窓口に電話すると予約ができる場合があります。
なぜこのようなことがあるのでしょうか。
これは夜行バスを含む予約指定制高速バスの座席は共同運行の各社で一定の割合で配分してそれぞれで管理しているからです。こうして配分して管理している座席を「持ち席」と言います。
「持ち席」配分は一般に出発地での発券が多くでるために出発地の担当会社に多く配分されています。
出発の前日ぐらいに、「手じまい」という作業を行って共同運行各社の座席予約状況を集約します。その後は出発地側でのみ座席を管理します。もう一方の会社から予約が入る場合は、座席を管理する会社に連絡して予約を入れることになります。
このようなシステムになっているために、1つの会社の「持ち席」が「満席」となっていても、別の会社では「空席」多数…ということもありえるわけです。
ただし、「発車オーライネット」対称路線の一部などではオンライン上でリアルタイムで一括管理している場合もあります。
(なお、座席予約受付の仕組みについての詳細は三共システム工房のページで解説されています)
「ダブルトラック」や「近隣の路線」に着目
ある地域からある地域まで行く路線に、複数の系統が存在している場合があります。
たとえば「大阪-鹿児島」を例にすると近鉄バスが運行する「トロピカル」号と、阪急バス・南国交通が共同運行する「さつま」号があります。
この2つは大阪付近や鹿児島市内での停留所に若干違いこそあるものの、大阪-鹿児島というほぼ同じところを走っています。このように同じ地域から同一方面の行き先へ複数の系統が存在する路線のことを「ダブルトラック」と言います。
東京-岡山のように3つ存在する場合は「トリプルトラック」と呼ばれることもあります。
もしこのような「ダブルトラック」「トリプルトラック」路線であれば、片方が満席でももう一方が空席が残っている…という場合があります。
たとえば「トロピカル」が満席でも「さつま」に空席が残っている可能性があったりするのです(もちろんその逆だってありえます)。
東京-大阪の場合はもっとバリエーションがたくさんあります。
東京は大きく分けて東京駅・新宿駅・そして池袋とターミナルがあります。
また大阪も大別してキタ(大阪駅・梅田)とミナミ(難波・天王寺・阿倍野・USJ)があります。それぞれ相互間を結ぶ路線がたくさんあるのです。
その他、さいたま(大宮)から東京の赤羽・奈良を経由して大阪へ行くような系統(国際興業・奈良交通「やまと」号)も存在します。
東京-大阪間の路線は、東京(または大阪)をちょっとだけ「かする」ような路線までいれるとこれだけあるのです。
そのため、1つの系統でダメだとしてもいくつもの選択肢がありますので次々あたってみるとよいでしょう。
また、首都圏や関西圏など大都市圏発着の場合、自分の乗りたい路線がうまく予約できなかった場合でも近くから出発する(あるいは近くに到着する)路線に着目します。
たとえば東京の場合、山手線内から電車を使って500円程度で行ける八王子・横浜や西船橋(千葉線)などを発着する路線を考えます。
関西圏であれば大阪環状線を起点に考えると、神戸・京都(枚方)・奈良・堺などが視野に入ってくるでしょう。
たとえば大阪行きがダメでも、東京発ではなくて横浜発とか、あるいは神戸行きとか奈良行きであれば空席がある可能性があるのです。
当ホームページの「全国夜行バス会社(事業者)リンク集」などを利用してうまく適合する路線をさがしてみましょう。
北九州(小倉)へ行くときは「福岡行き」より「下関行き」
北九州といえば福岡県にある政令指定都市の一つです。しかしながら東京から北九州に直行するバス路線は存在しません。
この場合、福岡まで行ってから北九州まで移動する…という方法もありますが、北九州からは実は下関の方ががはるかに近いので、福岡行きの「はかた」号(西鉄)を利用してから北九州に向かうよりは
下関行きの「ドリームふくふく」号(サンデン交通・中国JRバス)を使ってJR九州の鉄道線で移動する方が安くて便利です。
もっとも東京発着以外の福岡発着本州夜行路線についてはすべて北九州を経由します。
夜行バスに乗るときには、自分の目的地やダイヤに合わせてうまく路線を選択しましょう。
空席がないのでやむを得ず…ということでなくても、このようなケースもあります。
たとえば、熊本から出張で大阪梅田付近に行きたいという場合を考えます。
「熊本から大阪」ということであれば、熊本-大阪・京都線「サンライズ」号が真っ先に思いつくところです。
が、この場合は「トワイライト神戸」号を利用して神戸(三宮)まで行き、そこから電車(阪急・阪神・JR)で大阪(梅田)まで移動するとわずかですが安上がりになります。まあ、せいぜいコーヒー1杯分の違いなのですが(^^;)。
「サンライズ」の運賃は熊本-大阪で片道10,300円、「トワイライト神戸」の運賃は熊本-神戸で片道9,800円なので
阪急や阪神の運賃310円(JRの場合390円)を足しても安上がりなのです。
→「あなたも乗ろう!夜行バス」Index
-
「夜行バス」の基礎知識
-
乗車便の決定と乗車券の予約・購入
-
いよいよ当日!夜行バスの乗車まで…
-
夜行バスの車内について
-
消灯・そして到着
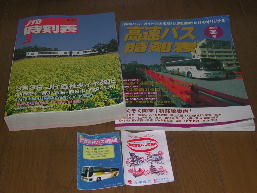 夜行バスをはじめとする高速バスの情報を入手する一番確実な手段は、やはり「時刻表」です。
夜行バスをはじめとする高速バスの情報を入手する一番確実な手段は、やはり「時刻表」です。